
全国で増え続ける空き家問題は、今や社会的課題として広く認識されています。しかしその一方で、「空き家」を新たなビジネスや地域再生の資源として活用する動きが活発になっています。古民家をリノベーションして宿泊施設や飲食店として再生したり、地域の人々が集う交流拠点に生まれ変わったりと、創意工夫次第で可能性は無限大です。
本記事では、全国で実際に成功している空き家活用の具体的な事例を取り上げ、その背景にあるアイデアや運営のポイントを解説します。空き家を再生するメリットや、実践に向けたステップ、利用できる補助金情報などもご紹介。「ただの古家」を「価値ある資産」に変えるヒントを見つけていきましょう。

空き家を放置してしまう=老朽化や治安悪化といったマイナス面ばかりが目立ちがちです。しかし、見方を変えればそれは“眠れる資産”です。地域の魅力を引き出す場や、収益を生む仕組みへと再生させた成功事例が全国各地にあるのをご存じでしょうか。
ここでは、実際に空き家を活用してビジネス化や地域貢献を果たした事例を4つ紹介します。宿泊施設、シェアスペース、賃貸住宅、地域交流拠点など、活用モデルにはそれぞれ戦略と運営の工夫があります。
観光ニーズの多様化により、空き家を宿泊施設として再活用する動きが増えています。特に「地域体験」や「暮らすように旅する」といったスタイルが注目される中、古民家や町家の温かみを生かした宿泊施設は、国内外の旅行者から高い支持を得ているのです。
たとえば、とある県の山あいにある築80年の古民家をリノベーションし、一棟貸しの民泊として再生した事例では、地元の職人が手掛けた家具や木材を活かし伝統とモダンが融合した空間を演出させました。宿泊者は囲炉裏での食事体験や田植え、薪割りなどの地域体験に参加し、「暮らすように泊まる」スタイルを満喫できます。地域住民との交流が新たな観光資源となり、地域経済の循環にもつながっています。
別の町では、古い町家を1階カフェ、2階ゲストルームとして再生する二毛作モデルも成功例の一つです。宿泊客が朝食を取るカフェが地域住民の憩いの場にもなり、観光と地域コミュニティをつなぐハブとして機能しています。
運営面ではAirbnbやBooking.comなどのオンラインプラットフォームを活用し、世界中の宿泊者を集客。レビューを通じて信頼を積み重ね、リピーターを増やす工夫も欠かせません。初期投資こそ必要ですが、地域資源と物語性を掛け合わせることで、安定した収益と地域活性化の両立が可能になります。
空き家の魅力をそのまま活かした「地域カフェ」や「コワーキングスペース」への転用も、全国で人気を集める活用方法のひとつです。古民家や築古物件の温かみを残しつつ、働く・集う・語らうといった多目的な機能を取り入れることで、地域の新しい交流拠点として再生できます。
たとえば、地方都市の駅近くにある古い商店をリノベーションし、昼はカフェ、夜はワークショップや読書会などのイベントが開かれる「コミュニティカフェ」として運営している事例があります。木の梁や障子をそのまま残した内装は、訪れる人に懐かしさと安心感を与え、地域外からの観光客も自然に集まるスポットとなったのです。
若年層やフリーランス層の増加に伴い、コワーキングスペースとしての需要も拡大しています。1階をカフェ兼イベントスペース、2階をワークルームや会議室として活用するなど、フレキシブルな設計が人気の理由です。高速Wi-Fiやプリンターなどの設備を整え、1時間単位のドロップイン利用を可能にすれば、誰でも気軽に利用できる環境を整えられるでしょう。
運営の成功には「人と人が繋がる仕組み」を作ることが重要です。例えば、地域のクリエイターによる展示会や、学生・主婦を対象とした講座を開催し、地元の交流を促進することで、利用者の定着と口コミ拡大につながります。
空き家をただ誰かに貸すだけの物件から、「シェアハウス」や「複数居室を持つ賃貸住宅」として再構築することで、収益化を大きく広げられる可能性があります。複数の入居者から賃料を得ることで、収入源を分散でき、空室時に収入がゼロになるリスクを抑えることができるためです。
実際、空き家をシェアハウスに活用した事例では「4部屋に改修して複数名で入居」という形で、一般賃貸と比較して収益性が高まったというデータもありました。
他にも、東京都内の一戸建て空き家をシェアハウスに改装したケースでは、「月々数万円から十数万円の賃料が得られる見込み」が示されています。また、学生向け・若手・シニアなどターゲットを明確にしたシェアハウスは、入居率も安定しやすく、地域貢献の観点から自治体が補助を出すケースも出ています。
空き家を賃貸住宅化・シェアハウス化することで、ただ所有しているだけでは生まれない価値を引き出せます。「どこか空き家をこう使えないか」という構想をお持ちなら、地域・ターゲット・コンセプトという3軸を意識して検討してみると良いでしょう。
地域のつながりが薄れつつある現代において、誰もが気軽に立ち寄り、世代を超えて交流できる「地域の居場所」の価値は、これまで以上に高まっています。空き家は、そんな温もりあるコミュニティ拠点として生まれ変わる可能性を秘めているのです。
実際に、古民家や空き家を改装して「地域の居間」として活用する取り組みが全国で広がっています。無料でお茶を楽しめるコーナーや、子どもが安全に遊べるキッズスペース、古本を自由に交換できる本棚などを設けることで、世代を問わず地域住民が自然に集える仕組みを作り出すことができます。
空き家を「福祉施設」へと転用する事例も注目されています。少人数で暮らせるグループホームや、サービス付き高齢者向け住宅として整備する活用方法です。こうした小規模施設は、入居者やその家族から「施設ではなく家のように落ち着ける」と高く評価されており、今後ますます需要が拡大する分野と言えます。
また、障害を持つ方の自立を支援するため、空き家を就労支援B型事業所などに活用する例もあります。古民家をリノベーションしてパンや焼き菓子を製造・販売したり、軽作業の場を提供したりと、地域と共に働く環境をつくることで、社会参加の機会を広げるきっかけにもなりえるのです。

前述のように、空き家活用の可能性は、想像以上に広がっています。飲食店や宿泊施設といった代表的な活用方法以外にも、地域のニーズや目指すビジョンに応じて、実に多様な選択肢が存在します。
ここでは、全国各地で実践されている空き家活用の多彩なアイデアを10パターンご紹介しましょう。
空き家を時間単位で貸し出すレンタルスペースは、初期投資を抑えながら多様な収益機会を生み出せる魅力的な活用方法です。最小限の改修で始められ、複数の用途に対応できる柔軟性が大きな特徴となっています。
レンタルスペースの活用パターンとして考えられるのが、住宅街の一軒家を多目的スペースに転換する方法です。平日の日中はヨガ教室や料理教室の会場として・夕方以降はセミナーやワークショップの場として、週末は撮影スタジオや誕生日パーティーの会場として活用することで、一つの空間が時間帯によって異なる顔を持ち、稼働率を高めることが可能です。
想定される利用者のニーズは実に多様です。企業の研修会場、ハンドメイド作家の展示販売会、地域の子育てサークルの集まり、音楽の練習場所など、用途は無限大です。
特に都市部では会議室やイベントスペースの需要が高く、手頃な価格で借りられる場所を探している個人や団体は数多く存在します。オンライン予約システムを導入すれば24時間いつでも予約を受け付けることができ、運営の手間も軽減できます。
空き家を小規模な商店として再生する活用方法は、地域に新たな魅力を生み出し、住民の日常生活を豊かにします。大型店舗では実現できない、店主のこだわりや個性が光る空間づくりができるためです。
小規模商店への活用として人気が高いのが、住宅地の空き家を改装したパン屋やカフェです。大きな店舗を構えるには資金が足りない場合でも、空き家を活用することで初期投資を抑え、独立開業の夢を実現できます。店内に数席のイートインスペースを設ければ、地域の人々の交流の場としても機能するでしょう。
ほかにも、雑貨店としての活用もおすすめです。地元作家の手作り雑貨やアクセサリー、地域の特産品を扱うセレクトショップは、観光客だけでなく地元住民からも愛されるでしょう。商品の仕入れから販売まで自分でコントロールできるため、店主の世界観を存分に表現できるのが魅力です。
小商店として成功するには、立地選びが重要です。人通りのある通り沿いや、観光地へのアクセスが良い場所が理想的ですが、住宅地であっても独自の魅力があれば口コミで評判が広がる可能性があります。
働き方改革やコロナ禍を経て、場所にとらわれない働き方が定着した現代において、ワーケーションやテレワークの拠点としての空き家活用は、大きな注目を集めています。都会の喧騒から離れた環境で、仕事と休暇を両立させたいというニーズは年々高まっています。
空き家をワーケーション拠点として活用する場合、最も重要なのは快適な作業環境の整備です。高速インターネット回線は必須条件であり、安定したWi-Fi環境がなければ利用者は満足しません。また、長時間のデスクワークに耐えられる机と椅子、適切な照明、集中できる静かな空間の確保が求められます。
立地の観点から見ると、自然豊かな環境にある空き家は特に魅力的です。海辺、山間部、田園地帯など、都市部では得られない景観や静けさは、ワーケーション利用者にとって大きな価値となるでしょう。
運営形態としては、短期滞在型の宿泊施設として運営する方法と、月単位での長期利用を想定したサブスクリプション型の二つが考えられます。短期型は観光要素も含めた利用が中心となり、長期型は本格的な二拠点生活やリモートワーカーをターゲットとしていますが、どちらの形態でもキッチンや洗濯機などの生活設備を整えることで、利用者の満足度を高めることができます。
少子化が進む一方で、多様な教育ニーズへの対応が求められる現代において、空き家を子どもや学生の学び場として活用することは、社会的に非常に意義深い取り組みです。特にフリースクールや学習支援の場としての活用は、地域の教育環境を豊かにする可能性を秘めています。
フリースクールとは、様々な理由で学校に通えない、または通わない選択をした子どもたちが学ぶ場です。不登校の児童生徒数は年々増加しており、学校以外の学びの場へのニーズは確実に存在します。
空き家を改装してフリースクールを開設する場合、何よりも安心できる居場所づくりが重要です。家庭的な雰囲気を残しつつ、学習スペースやリラックスできる空間、必要に応じてカウンセリングルームなどを設けることで、子どもたちが自分らしくいられる環境を作ることができます。
学習塾や放課後学習支援の場としての活用も有効です。特に地方では、近隣に塾がなく学習機会に恵まれない子どもたちが少なくありません。地域の退職教員や大学生ボランティアと協力し、低料金または無料で学習支援を提供することで、教育格差の解消に貢献できます。プログラミング教室や英会話教室など、特定のスキルに特化した教室として運営するといった手法もあるでしょう。
創作活動に適した場所を求めるアーティストや職人にとって、空き家は理想的なアトリエや工房となる可能性を秘めています。特に都市部では家賃が高く、創作活動のための広いスペースを確保することが困難なため、手頃な価格で借りられる空き家は魅力的な選択肢となります。
空き家をアート工房として活用する最大のメリットは、既存の住宅構造をそのまま活かせる点です。陶芸や木工、金属加工などの工芸作品を制作する場合、土間や庭があれば作業スペースとして活用でき、騒音や粉塵が発生する作業も近隣への影響を最小限に抑えられます。
さらに発展的な活用方法として、工房と展示スペースを併設する形態があります。1階を作品の展示・販売スペースとし、2階を制作工房とすることで、訪れた人々が作家の制作風景を見学できるオープンアトリエとして機能させることも可能です。
複数のアーティストでシェアする形態も注目されています。個々に工房を持つことが難しい若手作家たちが共同で空き家を借り、それぞれの作業スペースを確保しながら、共用の展示スペースやギャラリーを運営するという方法です。地域の芸術祭やアートイベントと連携することで、観光資源としての価値も高まり、地域活性化にも貢献できるかもしれません。
超高齢社会を迎えた日本において、高齢者向けのケアサービスや地域福祉の拠点としての空き家活用は、社会的ニーズが極めて高い分野です。大規模な施設とは異なり、家庭的で温かみのある環境を提供できることが、空き家活用の大きな強みとなります。
高齢者ケアの拠点として最も一般的な形態が、小規模な認知症対応型グループホームやデイサービス施設への転用です。比較的小規模な空き家を改修し、5名から10名程度の高齢者が共同で生活する、または日中を過ごすことができる施設を整備します。
住宅地にある空き家を活用することで、高齢者が住み慣れた地域を離れることなく、安心してケアを受けられる環境を提供できます。リビングやダイニングといった既存の生活空間をそのまま活かすことで、病院や大規模施設にはない家庭的な雰囲気を作り出すことができ、入居者やその家族からの満足度も高められるのです。
地域の高齢者が気軽に立ち寄れる交流拠点としての活用も重要です。「地域包括ケアシステム」の推進が叫ばれる中、高齢者の孤立を防ぎ、健康寿命を延ばすための居場所づくりが求められています。空き家をサロンやカフェのような交流スペースに改装し、お茶を飲みながら談話を楽しんだり、軽い体操教室や趣味の教室を開催したりする場として提供することで、高齢者の社会参加を促進できるでしょう。
観光のスタイルが「見る観光」から「体験する観光」へと変化する中で、空き家を活用した体験型観光施設は、地域の魅力を最大限に引き出す効果的な手段となっています。特に農村部や漁村部の空き家は、都市部では得られない貴重な体験を提供できる資源として注目されています。
農家民宿は、その代表的な活用方法です。空き家を宿泊施設として整備し、農業体験や田舎暮らし体験を組み合わせたプログラムを実施すれば、朝早くから畑に出て野菜の収穫を手伝ったり、地元の食材を使った郷土料理作りを体験したり、季節ごとの農作業に参加したりできます。子育て世代の家族や、食育に関心のある層からの需要が高く、長期休暇の時期には予約が殺到するケースもあるようです。
漁村部では、漁業体験と組み合わせた民宿運営が可能です。早朝の漁船乗船体験や、魚の捌き方教室、地元の魚市場見学など、その地域ならではのコンテンツを用意することで差別化が図れます。伝統工芸が盛んな地域であれば、織物や陶芸、木工などの体験工房を併設することで、文化的な価値も提供できるでしょう。
観光体験型施設として運営する際には、旅館業法や民泊新法、食品衛生法などの法規制を遵守する必要があります。特に農家民宿の場合、農林漁業体験民宿業として登録することで、旅館業法の基準が一部緩和される制度もあります。体験プログラムの内容を季節ごとに変化させ、リピーターを獲得する工夫も必要となるでしょう。
リモートワークの普及により、仕事と生活の境界が曖昧になった現代において、働く場所と住む場所を一体化させた空間への需要が高まっています。空き家を活用したコワーキング+住居併用型施設は、新しいライフスタイルを求める人々にとって理想的な選択肢となる可能性があります。
この形態の最大の魅力は、通勤時間ゼロの究極の働き方を実現できることです。2階や3階を居住スペースとし、1階をコワーキングスペースとして整備することで、階段を降りればすぐに仕事場という環境を作れます。
フリーランスやスタートアップ企業の経営者、クリエイターなど、場所にとらわれずに働ける職種の人々をターゲットとすれば、安定した需要が見込めますし、複数の入居者でコワーキングスペースを共有する形態にすれば、孤独になりがちな在宅ワークの環境に、適度な人との繋がりをもたらすことができるでしょう。
シェアハウスとコワーキングスペースを融合させた形態も効果的です。各入居者には個室を提供し、共用のリビング、キッチン、そして充実した設備のワークスペースを併設します。特にクリエイティブ系の職種が集まれば、デザイナー、プログラマー、ライター、動画クリエイターなど異なる専門性を持つ人々が協働し、イノベーションが起こる可能性もあります。
働き方や価値観の多様化により、都市と地方の二つの拠点を行き来する「二拠点生活」を実践する人々が増加しています。空き家は、このライフスタイルを実現するための理想的な住まいとして、大きな可能性を持っているのです。
二拠点生活向け住宅として空き家を提供する場合、完全なセカンドハウスとして売却・賃貸する方法と、複数の利用者で共同利用するシェア型の二つのアプローチがあります。
セカンドハウスとして提供する場合は、生活に必要な設備を一通り整え、いつでも快適に滞在できる状態にしておくことが重要です。家具や家電を備え付けることで、利用者は最小限の荷物で移動でき、気軽に二拠点生活を始めることができます。
シェア型の場合は、月に数日間の利用権を複数人に販売する「タイムシェア」という仕組みが考えられます。一人では維持費が高額になるセカンドハウスを、複数人でシェアすることで、手頃な価格で二拠点生活を実現できる方式です。
二拠点生活者をターゲットとする場合、地域との関わり方も重要なポイントです。単なる観光客ではなく、地域の一員として受け入れられるような工夫が必要です。地域のイベントやお祭りへの参加を促したり、地元の農家から野菜を直接購入できるルートを紹介したり、地域住民との交流機会を設けたりすることで、深い地域体験を提供できるかもしれません。
近年、地震や豪雨災害など自然災害が頻発する中で、地域の防災力向上は喫緊の課題となっています。空き家を防災拠点や一時避難所として活用することは、地域住民の安全を守る重要な社会貢献であり、行政や地域コミュニティからも高く評価される取り組みです。
空き家を防災拠点として活用する最も基本的な形態は、災害時の一時避難所としての機能を持たせることです。学校の体育館や公民館といった公式の避難所だけでは収容人数に限界があり、特に高齢者や乳幼児を抱える家族にとって、より身近で小規模な避難場所のニーズは高まっています。
空き家を耐震補強し、非常用電源や備蓄倉庫、簡易トイレなどを整備することで、地域の補完的な避難施設として機能させることができます。平時は地域の集会所やコミュニティスペースとして活用し、災害時には速やかに避難所に転換できる体制を整えておくことが理想的です。
防災資機材の保管拠点としての活用も重要です。発電機、投光器、救助用工具、担架、毛布、簡易トイレなど、災害時に必要となる資機材を分散して保管することで、一箇所が被災した場合のリスクを軽減できます。また、地域の防災訓練の拠点として活用し、定期的に消火訓練や救命講習、避難誘導訓練を実施する場所として提供することで、地域全体の防災意識を高めることにも貢献できるでしょう。
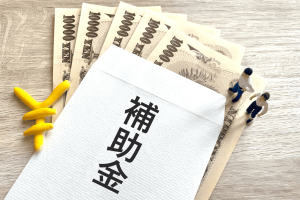
空き家を活用する際、最も大きな課題となるのが資金面です。改修費用や設備投資には相当な費用がかかるため、多くの方が二の足を踏んでしまいます。しかし、国や自治体は空き家問題を重要な社会課題と位置づけており、活用を後押しするための様々な補助金制度を用意しています。
国の主な補助金制度
自治体独自の補助金例
国の補助金制度について
増え続ける空き家への対策として、国は自治体を通じて個人や事業者を支援する仕組みを整備しています。国が大枠の制度を設計し、各自治体がそれを地域の事情に合わせて運用するため、所有する空き家がある地域によってサポート内容が変わります。具体的な申請方法や条件については、必ず空き家のある自治体の担当窓口で確認してください。
国の制度に加えて、市区町村レベルでも独自の補助金制度が数多く用意されています。解体費用、リフォーム費用、移住促進費用など、その内容は多岐にわたります。
例えば長野県長野市の「オフィス家賃等助成事業」は、最大1,000万円という手厚い支援が特徴です。中心市街地または中山間地域等の空きオフィスや空き家を借りて、新たに企業や個人が事務所や事業所を設置する場合に必要な経費全般をサポートしています。
東京都の「政策課題解決型空き家活用支援事業」は、最大250万円を補助する制度です。主に戸建ての空き家に対し、住宅政策の課題解決につながる改修をする場合に利用でき、改修に耐震対策が含まれる場合は最大450万円まで増額されます。
これらの補助金は、いずれもその年の申し込み件数によって予算が終了すると受付が締め切られてしまいます。そのため、早めに申し込み方法と要件などを確認しておくことが不可欠です。空き家を民泊として活用するときの補助金に関しては、以下の記事も参考にしてみてください。
>空き家を民泊にする際に活用できる補助金制度とは?採択されやすくなるポイントを徹底解説
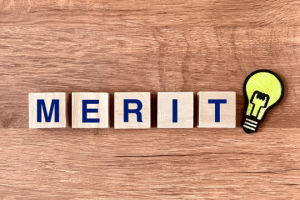
空き家活用は、単に遊休資産を有効利用するというだけでなく、所有者個人、地域社会、そして日本全体にとって多面的な価値を生み出します。しかし同時に、実際に活用を進める過程では様々な課題に直面することも忘れてはいけません。
本章では、空き家活用がもたらす3つの主要な価値から、同時に直面しやすい課題とその対処法についても詳しく解説します。
空き家活用によって得られる価値は、金銭的な利益だけに留まりません。
まず第一に、収益化の可能性です。空き家を賃貸住宅として貸し出せば、毎月安定した家賃収入を得ることができます。立地や建物の状態にもよりますが、適切なリフォームを施せば、月5万円から15万円程度の家賃収入も十分に期待できるでしょう。年間にすれば60万円から180万円という金額になり、固定資産税や維持管理費を差し引いても、大きな収益源となる可能性があります。
第二に、地域貢献という社会的価値です。空き家を活用することは、地域社会全体に良い影響をもたらします。荒れた空き家が魅力的な施設に生まれ変われば、周辺の景観が向上し、地域の印象が良くなります。特に過疎化が進む地方では、一つの空き家の再生が地域全体に希望を与え、移住者を呼び込むきっかけになることもあるでしょう。
第三に、資産価値の維持・向上という経済的な意義です。建物は放置すれば確実に劣化しますが、適切に手入れをし、活用し続ければ、建物の寿命は大幅に延びます。人が住み、日常的に換気や清掃が行われることで、建物は良好な状態を保つことができるのです。
現代のニーズに合わせたリノベーションを施せば、築年数が古くても高い資産価値を維持できます。将来的に売却する際にも、「活用されている物件」と「放置された空き家」では、買い手の評価は大きく異なります。空き家を活用することは、長期的な視点で見れば、あなたの大切な資産を守る最善の選択なのです。
空き家活用には魅力的なメリットがある一方で、気を付けなければいけないポイントも存在します。
最初に立ちはだかる課題が、初期費用と継続的な維持管理費用です。空き家を活用可能な状態にするためには、まず建物の状態を調査し、必要な改修工事を行わなければなりません。屋根や外壁の修繕、水回りの交換、内装のリフォームなど、建物の状態によっては数百万円規模の投資が必要になることもあります。
次に、法規制への対応という専門的な課題です。建物の用途を変更する場合(住宅を店舗や宿泊施設にするなど)、建築基準法に基づく用途変更の確認申請が必要になることがあります。飲食店を開業するなら保健所の営業許可、宿泊施設なら旅館業法や民泊新法に基づく届出、福祉施設なら介護保険法に基づく指定など、業種によって関連する法律は多岐にわたります。
最後に、実際の運営管理における課題です。賃貸住宅として運営する場合、入居者の募集、契約手続き、家賃の回収、トラブル対応、退去時の原状回復など、多くの業務が発生します。民泊や飲食店として自ら運営する場合は、さらに日々の接客、清掃、予約管理、食材の仕入れなど、本格的な事業運営のスキルも不可欠です。
これらの運営面での課題を軽視せず、事前に具体的な運営計画を立て、必要に応じて専門家やパートナーの力を借りることが賢明と言えるでしょう。
空き家活用を成功させるためには、テクニックやノウハウだけでなく、適切な心構え、すなわちマインドセットが非常に重要です。
まず第一に、長期的な視点を持つことです。空き家活用は、短期間で大きな利益を得られるような事業ではありません。初期投資を回収し、安定した収益を得られるようになるまでには、数年単位の時間がかかることも珍しくありません。しかし、そこで諦めずに継続することが重要です。
不動産は長期保有することでその真価を発揮する資産です。一時的な困難に直面しても、「10年後、20年後にどうなっていたいか」という長期的なビジョンを持ち続けることで、冷静な判断ができます。地域に受け入れられ、信頼を得るには時間がかかりますから、焦らず着実に積み重ねていく姿勢が成功への鍵となるでしょう。
第二に、学び続ける姿勢を持つことです。空き家活用に関する法律や制度は頻繁に改正されます。補助金制度も毎年内容が変わり、不動産市場のトレンド、消費者のニーズ、地域の動向なども常に変化することから、常に最新の情報をキャッチし、学び続ける必要があります。セミナーに参加したり、専門書を読んだりと行動を続け、新たな知識やアイデアを得る事が大切なのです。
第三に、地域との共生を意識することです。空き家活用は、決して運営者だけの利益のために行うものではありません。その建物は地域の中に存在し、周辺住民の生活環境に影響を与えます。
地域に受け入れられない事業は長続きしません。近隣住民への丁寧な説明と挨拶、地域行事への参加、地元企業や生産者との連携など、地域の一員として貢献する姿勢を持つことが不可欠です。「この事業が地域にとってどんな価値をもたらすのか」を常に意識し、地域課題の解決に繋がる活動を心がけましょう。

空き家活用には大きな可能性がある一方で、実際に一歩を踏み出すには様々な不安や疑問がつきまといます。「自分の空き家は本当に活用できるのだろうか」「どこから手をつければいいのかわからない」「信頼できる相談相手が欲しい」そんな悩みをお持ちの方に、ぜひご紹介したいのが「部屋バル」です。
部屋バルは、空き家や遊休不動産の活用を専門的にサポートし豊富な実績を有しています。単なる不動産仲介にとどまらず、物件の調査・診断から、活用方法の提案、リノベーション設計、施工管理、そして運営サポートまで、空き家活用に関わるあらゆる工程をワンストップで支援しています。
空き家という資産を眠らせたままにしておくのは、あまりにももったいないことです。しかし、一人で悩んでいても前には進めません。部屋バルの公式サイトでは、詳しいサービス内容や活用事例をご覧いただけます。あなたの空き家活用の第一歩を、部屋バルが全力でサポートいたしますので、まずは一度ご覧ください。